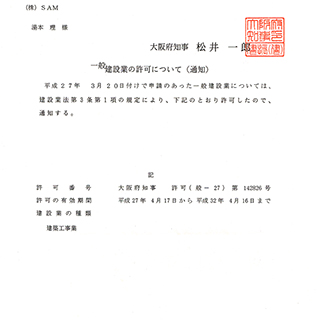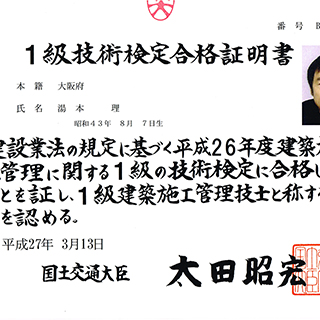子育て後に始めたいリノベーション ~40代から考える住まいの見直しポイント~

1. 子育て中と後、そして老後、住まいの悩みは変わることを予測しないと・・・
子育てがひと段落すると、暮らし方そのものが変わってきます。
子ども部屋として使っていた部屋が空いてしまったり、階段の上り下りがだんだん負担に感じられたり。
これまで当たり前だった家の使い方に、小さな違和感が出てくることも少なくありません。
私自身、長年リフォームの現場に携わってきて思うのですが、問題が発生して慌ててリフォームする方が後を絶たないので、40歳以降は「この先どんな暮らしをしたいか」「住宅のメンテナンス等も含めた資金計画」を考える大切な時期です。
老後を安心して過ごすためには、早い段階で住まいを見直しておくことが、急遽な補修や改装などを防ぐことができて、のちの安心につながります。
これからは、子育て中心だった生活から、自分たちのための住まいに切り替えるタイミング。
今のうちにできる工夫や備えについて、具体的に考えてみてはいかがでしょうか。
2. リフォームと住まいの維持に費用を抑えるには?!
子育てが終わると、日常の動き方や家の使い方が大きく変わります。
以前は子ども中心で必要だった広さ部屋数や収納も、今後はご夫婦やご自身の暮らしに合わせた形へ調整していくことが大切です。
住まいを見直す際にまず考えていただきたいのは、「これからの暮らしをどう描くか」ということです。
老後の生活を想定して、無理のない範囲で長く快適に暮らせる住まいを整えることが重要になります。
また、リフォームを計画する際には資金面も忘れてはいけません。
資金があるからできることだと思われている方もおられますが、資金が限られているから、絶対必要な住宅を老後も快適に不安なく過ごすために計画的に住宅に投資する方が急遽な出費も減り、長期的に見て出費を抑えられます。
物価は少しずつ上がっていくため、必要な工事を後回しにすると、結果的に費用がふくらんでしまうことも考えられます。
外壁や屋根といった定期的に行うメンテナンスも、資金計画の中に組み込んでおくことは必須事項です。
計画的に住まいを整えた方は、後から慌てることが少なく、暮らしにゆとりを持って過ごされています。
これからの暮らしをより快適にするためにも、ライフステージに合わせた見直しを検討してみてください。

3. 住まいを長く安く維持するための基本対策はこれ!
基盤を整える重要性
安心して長く暮らすためには、見た目を整えるだけでなく、家そのものの「基盤」をしっかりと保つことが欠かせません。
特に40歳以降でリノベーションを考える際には、将来を見据えて次のような点を確認しておくことをおすすめします。
外壁や屋根の寿命
まず大切なのが、外壁や屋根の寿命です。
外壁塗装は10〜15年ごとのメンテナンスが目安とされ、屋根瓦も30〜50年で葺き替えが必要になります。
ベランダや陸屋根のような平らな雨を受ける部分は、もっと周期が早く、10年ごとに防水処理を行うことが望ましいとされています。

配管チェックの重要性
次に、配管のチェックも忘れてはいけません。
水道管やお湯の配管、排水管はおよそ30〜50年が寿命と言われています。
過去の事例から言いますと、1か所配管がもれると、2,3年以内にさらにもう一か所漏れるという現象が多々あります。
これは水道管の寿命が来ているという証拠です。
水道管が漏れておれば、水が噴き出したり、雨も降っていないのに庭の地面が濡れていたり、水道料金が急に高額になったりで、水道管やお湯の配管から漏れてから少なくとも2か月以内には発覚します。
しかし、排水管は、漏れていても気づかないことが多いです。
割れが大きくなると庭が陥没してくることがあります。
排水管の周りの土が排水管内に流れて陥没するのです。道路や隣の家より地面が高いお住まいは、苦情がきたりして発覚します。
普段目に見えませんが、後から修繕するのは大掛かりになってしまいます。
リノベーションの機会に解体する箇所の床下配管はできるだけ交換し、その他の床下配管は、そこをリフォームするときに交換し、外回りの配管は、別工事で行っても費用はさほど変わらないので、資金が余裕があるなら交換、難しければ、今後の計画に組み込んでおきます。
耐震性とシロアリ対策
さらに、耐震性とシロアリ対策も重要です。
シロアリ害や材木の腐朽が、解体してからわかることがあります。
耐震性に影響しますので、補修補強工事が必要なのですが、解体してからわかることなので予算組をしていないので、お客様の指示がなければ、補修せずに仕上げる業者も多いです。
打ち合わせ時には不朽やシロアリ害は補修してもらうことを告げておき、解体時にはあなたの目で可能なら確認する方がベターです。
補強方法も適当では補強したことにならないので、耐震補強工事を行っている業者に依頼すると適切な補強方法を行ってくれます。
シロアリ対策は保険のようなものです。
何も起こらないお住まいは起こりませんが、7年から10年おきに対策を講じておくと安心です。
また、床下の湿気が多いお住まいはシロアリ害に合う可能性が高いので、防湿シートや防湿コンクリートを打つ、調質材や炭を置き定期的に取り換える、床下換気扇を設置するなどの対策が可能です。
耐震診断と補強の必要性
耐震に関しては、2000年以前に建築された建物は、耐震強度が「一応倒壊しない」という最低限の耐震等級1でなくても建てられた時代ですので、8割以上の建物が耐震強度が足りていません。
自治体の補助金があるので、少なくともリノベーション前に診断だけは行い、耐震補強工事の費用を算出してもらい、リノベーションと一緒に行うと費用を抑えられるので、この機会にできるだけ耐震補強工事を組み込みたいところです。
住まいの基盤を優先する
住まいの基本をきちんと整えることは、表からは目立たなくても、将来の安心を大きく左右します。
リノベーションを計画する際には、まずこの「基盤の部分」を優先して考えていただきたいと思います。
4. バリアフリーにできない!?そうならないためには!
昔と今のバリアフリーの考え方
昔は、バリアフリーでなくてもご高齢者様は生活できたので、大きな問題ではないと現在は感じられるかもしれません。
しかし、ご高齢者様やそのご家族とお話をしていると、足腰を痛めると数センチの敷居の段差を超えるのに非常に力が入り、神経を使うそうです。
無理をすると大事故にも繋がりかねないようです。
本当の意味でのバリアフリーリフォーム
バリアフリーのリフォームは、段差解消の代名名刺みたいになっていますが、本当の意味は”安全に自由に行き来できるようにするリフォーム”です。
具体的な例は
- 段差解消、段差減少
- 手摺の設置
- スロープの設置
- 各室温差の減少するための断熱リフォーム、危機の設置
などです。

各室の段差をどう解消するか
まずは、各室の段差部分をどのようにして超えていくかという方法から、ベストは段差をなくすことです。
行き当たりばったりで、一部屋づつリフォームしていくと、どこかに段差が残る可能性があります。
例えば、廊下からリビングへ移るにはバリアフリーにできたが、廊下から和室に入るには段差が残ってしまった…
玄関の框部分などの改修を含めた、1階の床を将来的にまでどのようにするか考えてからリフォームすると、順番にリフォームしていっても、最終的には段差がすべてなくなります。
スロープや手すりの工夫
どうしても段差解消リフォームができない場合は、段差をなくすために、小さなスロープを付けたり、手すりを付ける計画などが有効です。
足が悪いご高齢者様は、手すりにかなりの体重を乗せますので、壁の補強が必要です。
したがって、玄関部分から外へ出る部分には必ず段差が残りますので、単なる壁紙張替えのリフォームでも、手摺設置部の壁補強をしておくと安心です。

車いす対応の現実
将来的に車いすのことまで考えてという方もいらっしゃいますが、お若いうちに足が不自由になった場合は、パートナーがまだお若いので、夫婦間での介助も体力的に可能です。
しかし、過去の例では、ご高齢になってからの夫婦間の介助は、体力的に持たない方が多く、車いすのためのスロープを設置しても、すぐに施設に入られる方が多かったです。
スロープを作るのではなく、仮設スロープ板という介護用品がたくさん出ておりますので、経験上の持論ですが、考えない方がいいように思います。
介助が必要になったときの空間確保
車いすまでは必要ないが、手足が衰えた場合は、長く同居される方が多いです。
そのようになった時に、立ったり座ったりする場所は、介助者のわずかな助けで自宅で生活ができるようなので、介助者が入れる十分なスペースを確保しておくことで、介助が容易になります。
具体的にはトイレ、お風呂、玄関に十分なスペースを確保可能なら確保します。
狭小な住宅で難しいというお住まいでも、生活者はご夫婦二人なので、トイレと脱衣室の間の壁をなくし西洋風に、トイレと脱衣室を一部屋にして、お風呂と洗面室、脱衣室を少しづつ広くするなどの工夫次第でできる場合もあります。

5. 命と健康を守る「温度バリアフリー」
温度差が体に与える影響
段差の部分以外に、お住まいの温度を一定にするというバリアフリーがあります。
家の中での温度差は、思っている以上に体に負担をかけます。
特に冬場、暖かい居間から冷えた脱衣所や浴室へ移動すると、血圧の急激な変動で「ヒートショック」を起こす危険があります。
高齢の方にとっては命に関わるケースも少なくありません。
窓の断熱リフォーム
外気温の影響を一番受けやすいのが窓です。
窓から約50%外気温の影響を受けて、冬は特に室内が冷え込みます。
窓サッシには、断熱性でかなりのグレードがありますので、断熱性に注意してリフォームを行います。
内窓を設置して2重窓にすることが、一番簡単で安く窓の断熱リフォームをする方法です。
床と壁の断熱対策
次に床です。床のリフォームの際には、高断熱の断熱材を入れることにより解消します。
断熱材も窓と同様、グレードがたくさんありますので、綿密な打ち合わせが必要です。
また、床下の温度、屋根裏の温度が伝わらないようにするための壁内の通風がなくなるようにする、”気流止め”も重要です。
床を断熱しても壁に冷たいまたは、暑い空気が流れて室温が外機の影響を受けやすくなります。
部分断熱という選択肢
家全体を断熱改修するのが理想ですが、費用の面から難しい場合は、よく使う居間や寝室、浴室など、生活の中心となる空間だけを重点的に断熱する「部分断熱」も現実的な方法です。
断熱性能を高めることで、冷暖房の効きが良くなり、光熱費の節約にもつながります。
設備を活用した温度差対策
その他の方法として、浴室暖房や洗面脱衣室の暖房やエアコン設置、扇風機の設置もバリアフリーリフォームといえます。
光熱費はかかりますが、手っ取り早く温度差をなくす方法です。
暮らしを快適にする温度バリアフリー
温度バリアフリーは、一年を通して家の中の温度が安定するため、体への負担が少なくなり、暮らしがより快適になります。
断熱改修をされたお宅は「冬でも部屋移動が楽になった」「家の中で厚着をしなくて済むようになった」といった声をよくいただきます。
健康を守る意味でも、温度差をなくす工夫は大切なポイントになります。
6. 知らなかったー!家事をラクにする住まいの工夫
年齢に合わせた家事の工夫
子育てが終わった後の暮らしでも、家事の負担を少しでも減らす年齢に合わせた工夫が欠かせません。
毎日のことだからこそ、効率のよい動線づくりや設備の見直しが、生活のゆとりを大きく変えてくれます。
1階中心の生活を意識する
まず意識したいのが、1階中心の生活です。
将来的に階段の上り下りが難しくなったときに備えて、生活必需品はできるだけ1階で完結できるように配置しておくと安心です。
1階に寝室を置き、衣服の収納も1階に置くことを想定して計画します。
動ける間は2階で寝て、1階はくつろげる部屋にしておくのもいいかと思います。
いざ、体が動きにくくなる70歳後半になった時にリフォームを頑張ってするのもいいかもしれませんが、将来的には1階でほぼ生活が完結することができる計画をしておくと、容易に生活プランを変更することができます。
普段ほとんど使わない物は2階に収納し、必要な物、衣服類を1階に置けるようなクローゼットや小物の収納を作っておきます。
断捨離でリフォーム費用を抑える
不要な物のためにリフォームでお金をかけるのは無駄です。
このタイミングで、5年以上使っていないものを断捨離して普段の生活で必要な物を洗い出して、収納の計画を立てると、リフォーム費用も抑えることができ、生活スペースもすっきり広々となります。
洗濯や物干しの工夫
次に、洗濯や物干しの工夫です。
洗濯物を干すために濡れた洗濯物を持って、階段を上がり、ベランダのサッシをまたぐのは、お年を召してくると大きな負担になる家事の一つです。
1階に干すスペースを作る工夫が必要です。小さくても庭があるなら庭に、なければ腰窓の外に物干し金物を外壁や軒の天井に設置することも可能です。
洗濯機と一緒に売っている電気式の乾燥機が一般的ですが、時間がかかるし乾きもあまりよくなかったりするというので、やめる方も多いのですが、ガスの乾燥機は全く異なるものなようで、非常に優れモノでひそかなブームになっております。
コストも意外と安いようです。
家事動線の効率化
さらに、家事動線の効率化も大切です。
キッチンから洗面所、物干し場までの動きが短くなるようにレイアウトを見直すことで、日々の作業時間を短縮できます。
家事の工夫が老後の安心につながる
毎日の家事を楽にする工夫は、老後に向けた体力の節約にもつながります。
無理のない生活を続けられるように、早めに住まいを整えておくと良いでしょう。
7. 行き当たりばったりは出費が増える!リノベーション計画の立て方
快適さと将来への備えを両立する
リノベーションを考えるとき、大切なのは「今の暮らしを快適にすること」と「将来に備えること」を両立させる計画です。
目の前の不便さだけを解消するのではなく、長い目で見た資金計画や優先順位を整理しておくことが安心につながります。
資金の見通しを立てる
まず意識していただきたいのは、資金の見通しです。
物価や工事費は年々上昇しているため、必要なリフォームを先延ばしにすると、かえって費用がかさむことがあります。
短期的にローンを利用しても、早めに工事を行った方が結果的に負担が少なく済む場合もあるのです。
優先順位を決める
次に、優先順位を決めることです。
耐震や断熱、配管の更新といった住まいの基盤に関わる部分は、まず先に取り組むべきポイント。
そのうえで、バリアフリー化や家事動線の改善といった暮らしやすさを高める工事を組み合わせると、計画に無理がありません。
専門家への相談姿勢
さらに、専門家に相談する際の姿勢も大切です。
「どの工事を今やるべきか」「後でも大丈夫な部分はどこか」を率直に聞いてみると、より現実的なプランが立てやすくなります。
計画的な一歩を踏み出す
計画をきちんと整理して進めることで、安心して長く暮らせる住まいに近づきます。
将来を見据えた計画的な一歩を、早めに踏み出してみてはいかがでしょうか。
8. 定年後に行うか、40代・50代から計画するか~リノベーションで安心の暮らしを~
子育てが終わると、住まいの役割も少しずつ変わっていきます。
これからは、自分たちが安心して長く暮らせる家に整えていくことが大切です。
外壁や屋根、配管といった基盤部分のメンテナンスを計画的に行い、耐震や断熱で安全性・快適性を高めておくこと。
さらに、段差解消や水まわりの改善などのバリアフリー化、家事をラクにする工夫を取り入れることで、暮らしに余裕が生まれます。
リノベーションは大きな決断ですが、早めに取り組むことで費用や労力の負担を減らせます。
将来を見据えて住まいを整えることは、ご自身やご家族に安心をもたらす投資でもあります。
40歳からのリノベーションは、これからの人生をより豊かにするための前向きな準備です。
無理のない計画を立てながら、一歩ずつ安心できる住まいづくりを進めていきましょう。