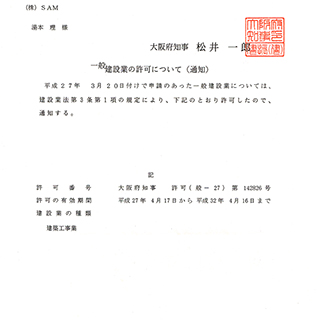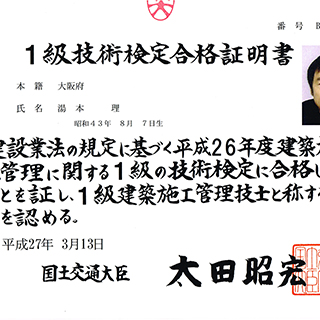20年のリフォーム監督経験から得た、予算とストレスを抑え、理想的に仕上げるリフォーム計画のコツ

「家のあちこちが気になるけれど、全体リフォームは予算的に無理かも…」
そう悩んでいる方、多いのではないでしょうか?
今回は、全体リフォームが難しいときにどう計画を立てればいいのか、具体的なコツや注意点をまとめました。
部分リフォームでも満足度の高い仕上がりにするために、ぜひ参考にしてみてください。
目次
1. まずはリフォームの“目的”を明確にする
一番大切なのは、業者目線ではなく「自分がどう暮らしたいか」をハッキリさせることです。
例えば…
- 部屋の壁紙、床をきれいにしたい
- 水回りの設備を一新したい
- 間取りを変えたい
- 大地震に耐える家に補強したい
- 収納を増やして家具を減らしたい
- 冬暖かく、夏涼しく過ごしたい
- 2階にトイレをつけたい
- 窓を増やして明るくしたい
- DKと和室をつなげてLDKにしたい
- 和室を洋室に変えたい
まずは、こうした「やりたいこと」をリストアップして、優先順位をつけましょう。
最初に方向性を決めておかないと、業者の調査後に、別の提案に目移りしたり、希望のリフォームが思ったより費用がかかったり、重要な補修必要箇所が見つかった場合などに、判断がブレやすくなります。

2. リフォーム中の暮らし方も考えておく
リフォーム中は騒音、ほこり、におい、通常の生活が送れないなどのストレスも多くなります。
リフォーム工事中、どこでどう暮らすかも大切なポイントです。
- 親族の家に住む(費用を抑えやすい)
- 仮住まいを借りる
- リフォームしない部屋で生活する(ただし、養生や作業調整で費用UPの可能性あり)
そして、家具や家財の移動先も確保しておきましょう。
ガレージや貸倉庫、親族の空き部屋などを活用できれば、作業スペースが広くなり作業効率が上がるため、工事費用にも良い影響が出ることがあります。
3. 予算は「余裕を持たせて」設定する
リフォームの予算は、ギリギリに設定しないことが大切です。
工事が始まると
- 腐朽した床下や壁の補修
- エアコンやカーテンなどのリフォーム以外の費用
- 思わぬメンテナンス費用(外壁の雨漏れ、屋根瓦の割れ、配管不良など)
といった追加出費が発生することが少なくありません。
また、今リフォームしない箇所でも、将来的に費用がかかる部分(外壁塗装や屋根の葺き替えなど)も考慮しておくと安心です。
4. 補助金・減税の活用は“目的に合っていれば”でOK
リフォームに使える補助金や減税制度もありますが、「補助金がもらえるからやる」というのは本末転倒です。
また、リフォームの補助金はマスコミで大々的に公開しておらず、一般の人には分かりずらい制度です。
申請や調査など面倒な手続きが多く、業者にとっても負担になるため、力を入れていなかったり、申請費用が高額になる場合もあるので、どういう補助金があるかだけでも調べられればベター。
親身になって相談に乗り、対応してくれる会社を選ぶことが大事です。
自分のリフォームの目的と補助金の条件がマッチしている場合のみ、上手く活用していきましょう。
5. リフォーム費用を抑えるコツ
ここでは、費用を抑えるためのちょっとした工夫を紹介します。
やる部屋・やらない部屋を明確に分ける
この部屋は天井だけリフォームしない、この部屋は床だけリフォームするなど、まだ綺麗だからリフォームなしで、と思っていたが、仕上がってみるとリフォームした箇所は新しくなり、残したところの汚れや黄ばみが目立つようになり、後悔する人も多いようです。
中途半端に部分リフォームするより、部屋単位ですべて行う方が仕上がりが綺麗です。
また、リフォームしない箇所の養生、境目は壊さないようにする解体費、一旦取外し元に戻す費用などの無駄も少なくなります。
不要な家具は事前に処分
廃材処分費も高くなっています。
自治体の施設などで処分すれば、費用を抑えられます。
家具が多いと、移動、養生、作業効率の低下などで費用が加算され、工事費が上がってしまいます。
リフォーム中は自宅で生活しない
仮住まいや親族宅を活用することで、養生費や小さな作業や作業現場での移動などが減り、作業効率が上がり、職人の無駄な手間代がカットできます。
仮住まい費、家具の引越し費用との比較をして、検討しましょう。
家財は別の場所に移動
ガレージや倉庫、空き部屋に荷物を避難させることで、工事の効率が大きくアップします。
また、リフォーム前に不要な家具や家財は、処分や譲渡するのも方法です。
家具が多いと、材木を加工する場所からリフォームする部屋が遠かったり、往来時間がかかります。
家具家財がないと作業スペースを取りやすく、リフォームする部屋で材料加工が出来るので、工事費を考慮、経費を考慮してもらいやすいです。

6. リフォーム箇所を決めるときの考え方
どのようにリフォーム箇所を決めるのか?順番に考えてみましょう。
①まず予算とリフォーム可能限度期間を決める
どれくらい費用がかけられるかと、仮住まいに住める期間、住みながらリフォームできる期間に限度があるならそれを出しておくと、リフォーム可能な範囲が決めやすくなります。
②妥協したくない場所には費用をかけ、他は低価格仕様にする
キッチン・浴室・LDKなど、使用頻度が高くこだわりたい空間は、設備機器やフローリングなどの建材のグレードを上げ、2階トイレ、納戸などの重要でない所は普及品仕様を選びましょう。
③金額と工事期間により「やらない部屋」も決める
いずれやるにしても、「今はやらない」と割り切ることで、予算、リフォーム中過ごす部屋、家具の移動場所の確保も出来るので、メリットも大きいです。
④床のリフォームも工事の仕方が3種類ある
床が傾きもなく、しっかりしていて、断熱も十分な場合
今のフローリングを下地板として、新しいフローリングを上貼りする。
フローリングがボロボロで下地として使えない、床断熱材を高断熱にしてほしい場合
下地、フローリングの貼り替え
傾きがある、カタツキや床下の湿気がある場合
束(つか、床下の柱のようなもの)から替える
このように、床、壁、天井は、仕上がりは綺麗でも、劣化度などに応じた施工方法で、耐久性や断熱性、水平、垂直の精度が異なります。
現状の状況とその部屋の使用頻度やご家族にとっての重要度により、しっかり調査してもらい、工事の方法を選べるように金額を出してもらいましょう。
7.メンテナンスが必要な部分も予算組みする
理想のお住まいにするために快適なリフォームをしたのに、完成後、別の場所で修理が多々発生すると、残念な思いをされると思います。
建材老朽化や風雨にさらされることにより劣化していたり、白アリや湿気で腐朽していたりと、年数が経っているお住まい程こういう箇所が多くあります。
- 外壁、屋根のメンテ不良により雨漏れ、外壁材が膨れてきた
- 配管から水漏れがした
- サッシの動きが悪い→歪んでいた
- 給湯設備が故障
- 雨樋と瓦が暴風で飛んだ
- 床を踏むと音が鳴る
費用がそこそこ掛かるものとして、外壁塗装や外壁材、ベランダの防水、屋根瓦、雨樋、基礎のセメント、窓サッシ、排水管、水道配管、お湯の配管、給湯設備など
リフォームの前に建物の全体点検をしてもらい、待ったなしの部分は今回のリフォームに予算組みしたり、今回のリフォームに関連する箇所があるなら、同時に行ったりと予算組みをします。
また、あと10年もしないうちに瓦を葺き替えなければいけない、5年後には外壁塗装が必要、などがあれば、その費用の事も考えて予算組みする必要があります。
8.住宅には性能があります
住宅には2つの大きな性能の差があることを知らない方もまだ多いようです。
①断熱性能
断熱性能の等級は7段階あり、断熱性能は2025年に初めて義務化されました。
等級4にしなければ住宅を建てることが出来ないという最低基準が制定されました。
それまでは、推奨基準のみで義務化は無いのであまり知られていません。
したがって、リフォームされる方のお住まいは現在の最低基準より低いお住まいが9割以上もあります。
光熱費が上がる中、無駄な冷暖房費を使っているお住まいがほとんどということです。
断熱リフォームで省エネで快適なお住まいになる可能性が高いと言えます。
②耐震性能
耐震性能は4段階あります(震度6以上の地震が発生した場合)
- 等級1以下 倒壊する可能性が高い
- 等級1 一応倒壊しないグレード
- 等級2 一応倒壊しないグレード
- 等級3 倒壊しない(病院、警察署などの耐震強度)
住宅を建築する際の最低基準の法律は建築された年度により異なります。
2000年以降に建築された住宅は「等級1以上」ですが、それ以前に建築された住宅は「等級1以下」の建物も多いです。
断熱、耐震性能を向上するだけのリフォームは大きな費用が掛かりますが、リフォームと同時に行うと非常に費用が抑えられる場合があります。
また、断熱、耐震の性能向上リフォームは、条件が合えば補助金と所得税の減税が受けられます。
リフォームの時にしか検討できませんので、一度検討してみてください。

“無理なく理想に近づく”ことが賢いリフォームです
全体を一気にリフォームするのが難しくても、しっかり計画を立てて目的を絞ることで、満足度の高い住まいづくりは可能です。
ポイントは、お住まいの状況調査をきっちりできるところに依頼し、工事内容を選択できるように見積りを出してもらいましょう。
- 自分にとって何が大事かを見極める
- 優先順位と予算をはっきりさせる
- 無理のない工事範囲で納得できる仕上がりにすること
焦らず、一歩ずつ理想の住まいに近づけていきましょう。